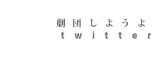『メーフ』出演者インタビュー 夏目慎也さん
富岡演劇祭での『メーフ』の上演を終えた出演者のおふたりに、劇団員の西村花織がインタビューさせていただきました!
劇団しようよの作品に、再演『パフ』から数度ご出演いただいている夏目慎也さん (東京デスロック)。
今回は、幼い4歳の少年「ガク」を演じていただいています。
これまでの作品と今回の作品のこと、大原渉平という作家・演出家の印象についてお話を伺いました。
富岡演劇祭『メーフ』公演終了後、福島にて
-富岡演演劇祭お疲れ様でした!それでは改めまして、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。夏目でございます。
-早速ですが福島公演はどうでしたか?
ざっくりしてますね!(笑)
-最初ですからね、ざっくりしたところからどんどんいきますよ (笑)
そうですね (笑)
ここに来るまではね、(富岡町での)初めての演劇祭だったので、ぶっちゃけどういうものなのかなんとなくしかわかっていない中で、自分たちに何ができるのかなということを模索して作ってきたようなところがあったんですが。
やってみたらとっても、お客さんもあたたかったですし、演劇もすごく、こう言ったらあれかもしれないですが、「ちゃんと観てくださっている」って。すごく良かったなあと思います。
1回きりの公演ですからね…「ぱっとやってぱっと帰ろう」って思っていたけど (笑)、でもやってみたらね、もうちょっとやりたかったな…みたいな気持ちが残るくらいに、お客さんや環境に恵まれた公演だったなあと思います。
-そうですね。後ろから見ていて、本当にいろんな方、関係者の方から地元の方まで観に来てくださっていましたし。
ね、幅が広かったですよね、すごく若い方からご年配の方まで来てくださっていて。
あの、台本の中でさ、「おばあちゃんになったら死ぬの?」ってセリフあるじゃない。「あ、おばあちゃんいるなあ」って思いながら客席見ていました。
こんな風に幅広い年代のいろんな人から観てもらえてね、よかったですよね。
-そうですね。
お子さんはいなかったな。
-ああ、小さい子はいなかったですね。
小さい子に観てもらっても面白い作品だなあと思ってましたけど。そこはいつかまたどこかでね、小さい子にも観てもらえる機会があれば。
-空気感のすごくいい客席で一体感があるような感じがしていましたね。
ね、めちゃくちゃよかったですよ。
-舞台上からでも感じられましたか。
まあお芝居やってる時はね、こっちもいろいろ考えたりしてるからあれだけど、でもまあ、感じるものはあったし、着替えるだけのシーンとかもね、あ、いやあんまりネタバレしちゃうとだめだよねこういうの (笑)
-いや、写真も出してるから大丈夫でしょう (笑)
そう?いい感じにしておいてね (笑)
そんなね、そんなじっくり着替えてるところは見てくれなくてもいいですよ~ただおじさんが今脱いでるだけですよ~って思いながらやってましたけども (笑)
でもねえ、ちゃんとお芝居を観てもらえて。それはそれで嬉しい話ですよね。
-おじさんが脱いでるところも (笑)、作品自体も、真摯に観てくださっている方が多かったなあと思います。
夏目さんは、この『メーフ』という作品の台本を初めて読んだ時はどんな印象だったんでしょうか?
なんか、あの~、まあ、えーっと…劇団…しようよ…様…
-様…?
に…出させていただいている中で…ね…
-ありがとうございます、お世話になっております…
えー…なんていうのかなあ。毎回こう、ギャラを5兆円もいただいているので出演しているんですけども…
-5兆円…はい、あの、いつもありがとうございます (笑)
ええ、あはは (笑)
なんかこう、毎回なんて言うのかな。まあ今回は「死」というひとつのテーマですよね。「死をどのように人は受け入れていくのか」っていう。新たに得るものがある代わりに、何をこう、彼は失うのかっていう。割と結構、劇団しようよに何回か出てる中で、共通している部分っていうものがあって。「なにかを失くし、何かを得る」みたいな。大原さんがそういうの好きなのかは知らないですけど (笑)
-知らないですけど (笑)
人間にとって大きな、すごく大きなテーマである「死」のね、「死の受け入れ方」っていうね。他者の死、(今回は)他者じゃないかな、まあ肉親かもしれないし、そういうことについて書かれていて、かつ、それって誰もが経験するから、絶対に。なので誰もが経験することだからこそ、普遍的というかね。みんながこう、「この道を通ってきたな」ってちょっとね、思ってくれたらいいなってね、本を読みながら思ったりとか。なんか、ね、思い出したり、お子さんがいらっしゃれば、これから小さい子たちがそういう経験をしていくっていうことについて、考えて、感じていただければ、いい作品ですよね、って思いながら読みましたねえ。
-実は、今お話に出たことが、大原さんもちょうど気になってるみたいなんです。夏目さんがおっしゃったとおり、「失われていくものと、また新しく得ていくもの」のような、すごく当たり前のことだけど、でも人にとって大きなテーマを扱って取り組んでいきたいっていうみたいな意思があるみたいで…
あら、そうなんですか。
-そうなんですよ、だから「あれ、質問ご存知でしたか?」ってびっくりしています。
あらそんなことありましたか (笑)
-大原さんの考えを汲み取ってくださっていて「夏目さんはすごいなあ!」って思いました (笑)
いやさすがだね僕 (笑)
-夏目さんは、この作品を通しても通さずとも、「失われていくもの」とか、「死」というものに対して、ご自身のお考えなどはありますか?
そうですねえ。えっと。なんというのかな、うまく言えるかな。
この物語の登場人物の「ガクくん」は、死というものの概念がまだ曖昧で、でも死というものをちょっとだけわかっているじゃないですか。それはでも、やっぱり、自分のことじゃないですよね。自分の死をどう受けるか、ではないですよね。僕自身で考えると、もちろん他人の死に向き合う局面ってのは人生の中で何回もあったし…いや何回もってことはないか、何回か、ですね(笑)、何回かあったし、幸いにも僕はまだ両親はご存命、なので。そこはまあ、あれなんですけど…僕は人生もまあ、半分以上も過ぎるまで生きていて、自分の死についても考えなきゃいけない時期に結構来てるんですね。
-はい。
で、自分の死の受け入れ方。
ガクくんは、ガクくんから始まって、死というものと付き合い始め、やがては、自分の死とどう付き合っていくか。その途中に、僕は今いるんだな。終わりに向けての、人生の終わりに向けての、もうひとつの死の付き合い方、ということを割と思ったりしました。…大丈夫ですか、言いたいこと伝わってますか (笑)
-もちろんです、伝わってます!そのお話からひとつ思い出したことがあって。この作品を見てただけたらわかるかもしれないんですが、ラストの演出が、「夏目んさん演じるガクくん」が「もしかしたら成長した姿」だなあとやっぱり思える気もして。
そうですよね。
-で、その「夏目さん演じるガクくん」が今なにを弔っているのか、もしかしたらそれはもう先に逝った「おじちゃん」かもしれないし、自分自身への祈りかもしれない、とかそういう想像を掻き立てられる瞬間でしたね。
いやいや、とってもよくわかりますよ。
-それから、今回の作品での「死」との向き合い方について、矢田さんはご自身が甥っ子さんと触れ合う時や、また矢田さんが今後お母さんになった時に、「小さい子にとっての、死と自分」っていう向き合い方の話をされていたんです。ここで、夏目さん・矢田さんが真逆の概念の向き合い方をされているなあ、と思いまして。お二人の俳優さんの中で真逆の捉え方の向き合い方をされていて、それ自体がバランスよかったのかな、と。稽古場で死の概念へのすり合わせってしたんですか?
あ、いやそれはしてないかなあ。
-ああ、じゃあやっぱり各々の感覚なんですね。
死について、考える…まあもちろんね、稽古場に3人いてそれぞれ考えているでしょうけど、それぞれに考えていることを、それぞれに考えたまま舞台上に乗せているような。そんなになにかこう、そのことについて…うん、まあよくわかんないや (笑)
まあでもそれについてすり合わせたり話し合ったりとかはなかったかな。
-そういうのがよかったのかな。お互いに感じ合う、みたいな、そういう空気感かもしれない。でもそうですね、俳優ってすべてをすり合わせはしないですもんね、お互いの立ち方を見て感じるというか。
でもまあ、今しゃべりながら思ったのは、「死」っていうのは最終的には「個人」として向き合うものだから。だから、その感じも、偶然だけど話し合わなかったことによって、「死」と「個」との向き合い方みたいな、その辺のことがこう、うまく、偶然にいったのかもしれませんね。
-充実した稽古ですねえ。
充実してたかなあ? (笑)
してたかはわからないですね! (笑)
-そうだ、稽古場で「斜めの関係」っていう話があったそうですね。
ああ、はい、そういえば僕言いましたね。話しました。
-それについて私にも教えてほしいなって思ったんですが…
これはもう、人様の受け売りというかですね、僕が読んだ本があって。
今回の話は「伯父さんとの話」じゃないですか。稽古場で、似たような作品についての話をちらっとしたんです。そこで出たのが、映画の『カモンカモン』っていう作品と、僕が面白かったって出したのが『旅する練習』っていう小説で…乗代雄介さんっていう方が書いてるんですけど。いずれも伯父さんと甥っ子、あるいは姪っ子との話が題材で。「斜めの関係」っていうのがどういうことかって言うと、例えば親と子の関係を「縦の関係」って呼ぶ。で、例えば、僕とかおりさん、他者、友達とか恋人っていう関係っていうのを「対等」とか「横の関係」とすると、叔父さんと甥っ子とかは、もうちょっと違う、いわゆる「斜め」。斜めですよね。親族で、まあ血は繋がっているかどうかはわからないけれど、親族だけれども、縦でも横の関係でもない、「斜めの関係」。親子ほど親密に踏み込むわけではないし、他人ほどお互いのテリトリーを頑なに守るわけではない、みたいな。間の微妙な距離感っていうのがあるんではないか、みたいなことを「斜めの関係」って話で。そういうのが出るといいですよねっていう。例えば、友達とかには言えないことが伯父さんには言えるとか、伯父さんも、普段他人と接するのとは違うやり方で自分の甥っ子と接するとかね、そういうことがあるんではないか。とかね。そういうような話を稽古場で話したように思いますね。合ってるかなあ (笑)
-なるほど、そういう感覚って稽古の中で結構活かされていたりするんですか。
そうですねえ…
-大原さんも意識しながら作っていた感じはあるんでしょうか。
どうだろう。意識的にはしてなかったかもしれないけれど…その、なんて言うかな、戯曲にも出てくる大原さんの飼っていた犬「ミューの話」とか、ああいう話とかは、いかにも伯父さんがしゃべりそうな感じっていうか (笑)
-たしかにそうですね (笑)
僕なんか子どもいないからわかんないけど、子どもに言うというよりは、親戚の伯父さんが言う話っぽいなあって感じはあって。それはやっぱり、そういう関係だから出る話っていうか。大原さんがどれだけ意識してたかはわからないけど、そういうものが出ているなあと僕は思いましたよ、戯曲の段階で。あとなんだろう、最後について。何回か書き直されているんだけれど、なんかね、あの、おしっこをさ、しちゃいそうになる子どもに対しての態度みたいなものね。そのあたりについても、親だったらできないことも、伯父さんだから言えることもある。まあ逆もあるというか。ガクの方も、お父ちゃんとかお母ちゃんには言えないけど、おじちゃんには言えることみたいなことも感じた、そういう関係で出てくるセリフがこの作品にはあるんじゃないかなあ。
-最初にあった台本と、実際上演した台本って、書き換えたり増やしたりが結構多かったって聞いたんです。そうだったですか?
いや、えーっとね、ちょこっと途中で変わったっていうのと、やっぱり大きく、大原さんが変えたというか、どのようにするかを迷っていたのはラストだったから。まあ、大原さんって毎回ラストを迷うよね、締め方をね。まあね、どのように終わらせるかっていうのはとても重要ですよね、作家さんにとっては。俳優はそんなに思ってなかったりするけど (笑)
-早く決めてよってね (笑)、もうすぐ本番日だよ!みたいなね (笑)
これはネタバレですけど、最初の台本ではガクはおしっこ漏らさないし、ひとりでトイレに行くって行ってひとりではけていく、っていう最後だったんですけどね。
-ああ、じゃあもう作中でそのまま成長した姿、みたいなのが見える話だったのかな。
そうそうそう、そういうことなのかな。でもなんて言うんだろう。「そうはいかないよね、人間ってね」ってところにね、引っ掛かる感じがね、すごい大原さんっぽいっていう。
-わかりますよ。
そこは作家として、すごくいいところだと思います。ああ、こういう終わり方になるのか、っていうのがありましたね。
-今回、大原さんの作品に出ていただくのがもう4回目になりますね。
そうなんですよ、4回目ですよ…毎回5兆貰ってるからもう、20兆円ですよ。国家予算くらい貰ってますからね。ありがとうございます。
-こちらこそ本当にありがとうございます。大原さんと最初に関わった時から変化したなあ、ってところは何かありますか?俳優の立場から見て。
いやあんまない。
-あんまないですか (笑)
うそうそ(笑)
最初の、なんかね、えーっと、たぶん大原さんの作品を観たのが、『パフ』だったんですよ、王子小劇場の。
-人形劇でやってた方の『パフ』ですね。
そうそう。怪獣が街を壊す話だったかな。
-そうです、そうです。
それを拝見し、そのあと最初に大原さんの作品に出たのが、せんがわ劇場の海外の戯曲をリーディングするっていう企画だったんですね。その2本がね、始まりだったので。リーディングはね、戯曲があって、そこに演出をつけるっていうことだったじゃないですか。で、(人形劇の)『パフ』も、なんていうかな、演出が斬新だった作品っていうか、いわゆるストレートなプレイじゃない、何かを何かに置き換えたり、違うものに見立てたり、レイヤーがいっぱいある作品だったから、「この人は演出も脚本もやるけど、すごく演出にこだわる」、そのようなタイプの方なのだろうと僕は勝手に思って参加したら、実は戯曲にめちゃめちゃこだわっていた、ていうのが、(2018年に再演の)『パフ』に参加した時に判明するわけですね。何回も何回も書き直し。ラストも何回も書き直して (笑)
-はい (笑)
で、「なるほど、戯曲に、言葉を扱うのにすごくこだわる方なんだな」って考えなおしたんです。
-そこで夏目さんの中で、印象が変わったっていう。
そう。僕の中で、大原さんの印象が大きく変わったのが、せんがわ劇場でのリーディングの次に参加した『パフ』だったんですね。その時の印象が今回も引き続いているっていうか、なんというか、戯曲、言葉、とか、そういうことにこだわる。今回特にね、関西弁っていうのが1つ大きな要素としてあってね。
-そうですねえ。
大原さんっていつも、大原さん本人を投影する戯曲を書くので。彼の人生で起こったことをヒントにフィクションを書いていくっていうので、関西弁で、かつ、方言指導もしてくれて、より実存に近い言葉になったというか。フィクション度合いが大原さんに近づくような印象があったかな。方言によって。
-大原さん、以前は関西弁の台本ばっかりだったんですよ。
そうなんですか。
-わたしも関西弁しゃべれないのに関西弁しゃべれって言われてたので、ひぃひぃ言いながら練習しました。
いやね、ちょっとね、関西弁に関してはね、まだちょっとアレだった…今後の課題としてね…
-いやいや、夏目さんも方言に馴染んでらっしゃいましたよ。
本当ですか (笑)
でもね、方言にする効果、みたいなものもね。標準語のニュアンスだと表現しにくいこともあって、それについて、細かく追及したいのかなあとか思いながら。本人に聞いてはいないですけど。そういうことからもね、言葉にこだわる人なのかなあってことは感じていましたねえ、稽古で。
-実は大原さん「僕は脚本書きたくないんだ、演出やりたいんだ」って言ってるんですよね。でもわたしもどちらかというと今は脚本先行という印象あるんです。夏目さんは、”演出家の大原さん”についてはどんな印象ですか?
ええ、どんな印象だろう。なんかあの…戯曲は、彼の人生の一部分を書いているので、すごくいいものだなあ、彼のプライベートっていう感じがするっていうか…演出に関しては…これは怒られるかもしれないけど…彼の周りの、彼が見てきたものにすごく影響を受けている演出だなあって。うん、なんて言えばいいのかなあ…「これぞ大原演出!」みたいな印象は薄いかなあ…そこから一歩抜けられたら、演出家としては結構面白い方になるんじゃないかなと思います。
-ああ、なるほどなあ。夏目さんが最初に観てくださった、人形劇でやった『パフ』まではわりといろんなことを試してみたい、ストレートにするだけじゃない何かを求めているような気がしていたんですけど、あれが終わってからはあんまりそういう方向を好まなくなったような印象があって。
ああ、なるほどね。そうですよねえ、確かに『パフ』の再演は、いわゆる「静かな演劇」でしたね。
-そうなんですよ、静かな演劇をしたいっていう。密な時間を作りたいって言ってて、時間が飛ぶとか、レイヤー多い、みたいなものはやらないっていうような。でもまあ、大原さんの中でどうしてもレイヤー多いものになっちゃったりとかあるみたいですけど(笑)、でもその辺がこう、いろいろ変わっていって…前のやり方も、わたしは好きだったので。なんかいろいろ大原さんの中で最終的にガッと融合したらもしかしたら、大原さんの個性の、っていうものが出てくるんじゃないかなあって。
あ、でもそれはすごく思いますよ。一緒にやってて思うのは、「途上の人」っていうか。演出で言うとね。まだ完成させてない人であり、そこは結構、一緒にやってて面白い部分でもある。「ああ、彼は今こういうことを思いついて、こういうことをやった」みたいなね、「面白いことを考えるなあ」って思うことすごくいっぱいあるし。
いいじゃないですか。演劇人生長いですから。長い時間をかけて、やっていったらいいことではないかなあとね、思いますよね。
余計なこと言っちゃったかなあ…
-いやいやそんなことないです、率直な感想をありがとうございます。
演劇の話をするのって大変だねえ…
-ではそろそろ時間も迫っているので。今回この公演を機に、劇団しようよは本拠地・京都と仙川の2拠点で活動していきたいと考えているんです。
あら、そうですか。
-それで、大原さんは東京の俳優さんたちともっとたくさん出会いたいと思っているようなんです。よければ、俳優さんたちに向けて、大原さんのおすすめポイントとかこりゃあかんでポイントなど、なにかコメントをいただけませんか。
大原さんに対して思うことは、彼はすごく繊細な人だなあってところが第一印象としてあり、そこが彼のすごくいいところなんですよね。で、常に、こう、なんなんだろうなあ、なんかこう、うーん…そうね…(笑)
うん、繊細。そこは面白いので。戯曲とかも読んでもらったり、お芝居観てもらったらすごくよくわかると思うんだけど。細かいこう、なんていうのかなあ、繊細であるが故に、ひねくれた世界の見方をしているというか、そういうところが結構ある。僕はそこがやってて面白いと思っていて。変なやつがいるな、って見てもらえたらいいんじゃないかな。
―ありがとうございます。では最後に、東京での再演にむけて何か一言お願いします。
再演に向けて…あの…関西弁を… (笑)
-関西弁ですね (笑)
あはは (笑)
いや、結構いろんな人に見てもらいたい作品には仕上がっているので。ぜひ。
これも誰かの受け売りではあるんですけども。演劇っていうのは「世界を表わすものである」ので、僕たちが見たいものも舞台上にあるけれど、見たくないなあと思うものもあるんですよね、舞台上に。で、そういうものがあるから、演劇っていうものは面白いと僕は思っていて、大原さんはそこを逃げずにちゃんと書くというか。醜いものを醜いままぶつけたい、見せようとしていらっしゃる一面がね。これは『セミへブン』の時からの一連の流れだと思うんですけど、今回もまあ「死の受け入れ方」ということに対して、登場人物二人とも、「ガク」だけじゃなく「僕」も、どのように死を受け入れようとしているのかっていうところを、もうちょっと深く掘り下げていきたいなあと思います。まあ最終的には関西弁を頑張ろうと思います(笑)
-わかりました (笑)
こんなところで大丈夫ですか (笑)
-ありがとうございます。いいお話を聞かせていただけました。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2011-2017 Copyright ©劇団しようよ All Rights Reserved.